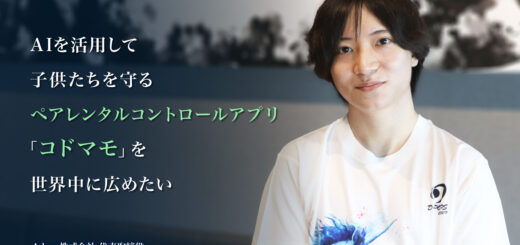1on1ミーティングのススメ
超久しぶりに、noteに記事を書きました。
https://note.com/rouhei/n/n27a3d8bf8483
1. GenZeeの経験
1:1の文化というのはシリコンバレーからもたらされた、と言われています。GenZeeは、2007年の10月にGoogleに入社した時には、既にGoogle社内では絶対的な推奨業務として1on1ミーティングが浸透していたので、シリコンバレーの中でも、1on1の発祥はGoogleこそが起源だと思います。(ちなみに、Facebookの主要幹部とマネージャーはGoogleから大量に移籍したメンバーなので、FacebookもGoogleから1on1を輸入しています。)
さて、2007年のGoogle入社、本社の上司とその部下として1 on 1を受け、日本のBizDevのリーダーとして、APACのリーダーとして、また、Google Japanの幹部として、上下の関係でも、横(関連部門の部門長)の関係でも、定期的に1on1を実施していました。
サブプライムショックがあったり、FBの脅威があったり、リストラがあったりというタイミングで、事あるごとに、全世界のマネージャーには改めて1on1の実施を徹底する旨のアナウンスがされたものです。
また、その後カカクコム社に転職した後も、当時まだ1on1文化が無かった会社でしたが、上司であった社長に、GenZeeと1on1を実施していただくようお願いしましたし、その後社長からの指示で、全社で1on1の実施が徹底されることとなりました。
という経緯で、2007年以来、2023年に会社員を一旦引退するまでの16年間、マネージャーとして、1on1ミーティングを実践してきました。
ちなみに、日本ではヤフージャパンが2012年頃から導入したとの記事がありました。当時の社長の宮坂さんに確認すべきですが、これはおそらく、2010年にYahoo! JapanがGoogleのエンジンを採用するというビッグディールを結んで以来、両社の交流が始まったのを機に、いくつかのGoogleの文化を輸入したからではないか、と思います。
2. 1on1の進め方
1) 時間と頻度
組織の規模や文化にもよるので、絶対的なルールというものはありませんが、Google社を例にとると、大体以下のようなものでした。
・時間は30分。最大60分。長ければいいというものではない。
・直属の部下とは週に1回実施。(平均10人くらいまでならば)
・2階層下の社員とは月に1度実施。
・大きな組織でも年に一度は全員と実施。
・定期的に実施し、年間を通じて継続することが重要。
2) 話し合う内容
概ね、以下のリストの順番に質問をしたり、話題を順次変えていきます。一方、長期的視点で見た時のその重要度は下から順に重要です。
・全社に徹底すべきことの再確認。
・マネージャー(自分)から個々人にアサインした、もしくは他部門連携プロジェクト等で抱えているタスクの進捗の確認。
・営業や開発、顧客対応など、職務に関しての、個別具体的な相談。
・人事関連のうち、個別に伝えるべき事項。
・社内で気になることはないか?というヒアリング。
・キャリア開発に関しての話し合い。(毎週ではなく、1ヶ月~四半期に一度程度実施)
・最近どう?困っていることはない?という感じの何でも雑談。(実はこれが一番大事)
3) 面談相手
・基本的には組織上の自分にとっての上司と、自分にとっての部下との間で実施する。
・マネージャー側から見て、もう一階層下のメンバーとの1on1も実施することが好ましい。距離が離れないためや、彼らの直属の上司の問題や評価を把握するため。この場合の頻度は四半期~半年に一度程度。
・類似部門、協業する部門の同じ立場のマネージャー同士で。共通する課題のお互いの相談や、お互いの上司同士で話し合ってもらいたいことのすり合わせ等をするため。
・その他、特に組織に縛られることなく、この人とは定期的に情報交換したい、と思う人がいれば、月1程度の1on1実施をお願いしたり、されたりした。こちらも企業や組織の規模にもよる。GoogleのDirector職の時は、APAC地域の各国のビジネス開発部門の代表や、米国本社やAPAC本社の関係部門のマネージャーなどと実施していた。
3. 1on1の効用
1) 組織のタスク漏れリスクが減る
部下全員と実施しながらそれぞれが認識している自分のタスク、というのをマネージャーとして聞いていると、意外とタスク漏れがあることに気付かされる。これって私じゃないです、誰かほかの人がやると思ってました、的な重要な仕事。直属の部下と週次で1on1を実施することにより、このようなタスクの漏れを防ぐことができます。
2) 潜在的な問題の事前把握ができる
大口顧客との関係が揺らぎ始めているとか、取れるつもりでいたディールを落とす危機に来ていることにメンバーが気付いていなかったということを早期に検知ができます。経験的にも1:1を実施している中で、そういう事象は洗い出せるもの。チームミーティング等でまだ30%くらいのリスクをあえて報告しない、できないメンバーもいるものなので。
3) 個人的に抱える問題を認識できる
信頼関係を築くと、本人や家族の病気のこと、家計の問題、悩みなどを明かしてくれることがあります。医者や法律家や財務アドバイザーではないので、解決することはできないし、しようとしてはいけないけれども、その悩み、問題を受け止めることで、どういう状況、どういう気持ちで業務にあたっているか、を理解しながら指示ができるのと、無感情で指示をするのとでは、チームマネジメントとして大きな違いが出てきます。
4) 退職予備軍を検知できる
そろそろ異動したがっているとか、転職活動を始めているということを、自ら言ってくれるケースもあるが、言わないケースでも、定期的に話を聞いていると、大体読めるものです。早期検知が解決(慰留)の秘訣です。
5) ガス抜き
愚痴でもいい。聴いてあげることの効用は大きいです。言いたいことを話したら、すっきりしてまた翌日からバリバリ前向きに働く、という人は多いです。ガスを抜いてあげましょう。会社の方針が、多くの社員が納得できないものであり、でも、幹部としては徹底しないといけない、ということは会社や社会にはあるものです。マネージャーが表立って愚痴っていてはいけません。部下の率直な愚痴を聴いてあげたうえで、自分自身の前向きな捉え方、考え、今後の取り組み方などをシェアすると、場の空気が少しずつでも前向きになります。
4. 注意すること
1) 心理的安全性を保つ
話してくれたプライバシーに関わることは、もちろん口外しない。
昨今よく言われる、「心理的安全」を保つことは特に重要です。それを裏切ると、二度と本音を語ってもらえなくなります。
2) 公平性を保つ
一人の社員から聞いた、他の社員の不満や悪口や噂話を鵜呑みにしない。
当然のことながら、人には好き嫌いもあるし、特定の個人間に生じた摩擦があるものなので、一人からの意見に左右されないよう気を付けましょう。
3) 安易にコミットしない
本人の希望を何でも聞けばいいというものではない。
中には、会社の不満を延々と話す人、提案や議論ではなく、批判を繰り返す人、初面談で、”私は有能だ、給料を上げてくれ”という人(外資系企業にありがち・・。)初面談の時などには、ここぞとばかりに自己主張や不満をぶつける人がいる。でも、すぐに否定せず、まずは聞く。一方で、何でも言えば通る、と勘違いしないよう、安易にコミットしない。あの時約束してくれました、などと言われぬよう、気を付けてコミュニケーションをしましょう。
4) 目的意識を持つ
自己満足にならぬよう気を付ける。
1on1さえしていれば事業運営がうまくいくものではありません。そんな訳はありません。事業運営の推進の妨げを抑止することができるものくらいと考えましょう。管理職のメインの仕事、1on1を実施することが最優先と、頭がガチガチになってしまうと、顧客対応や緊急障害対応、重要な採用面接を優先したいという部下に対して、1on1があるから後回しに、などと間違った判断をさせてしまう。マネージャーが実施する1on1は、自分のためではなく、部下のために行っている、ということを忘れぬように。実施は柔軟に。延期や日程再調整も柔軟に。